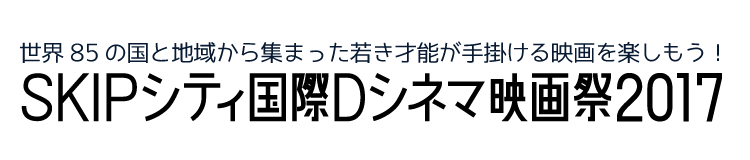妻の死後、養子である息子に愛を注げなくなった父。少しずつ正面から向き合い始める 2 人を描きながらも、貧困・格差・人権など様々な問題にも焦点を当ててゆくノルウェー作品『愛せない息子』で脚本を担当したヒルデ・スサン・ヤークトネスに単独インタビューを行った。
非常に興味深い経験をです。単なる旅行ではなく、日本に映画をお見せするというミッションとともに、他国の映画、その世界を垣間見るということもできています。そして私たちの作品への反応や、映画祭の運営に、「日本文化」というものを体感しています。映画祭では、全てのプログラムが綿密に計画され、全ての方がお客様のためにも、ゲストの為にも全力を尽くしてらっしゃることに満足しています。
―今回が初来日ですか?映画祭の他に何かされましたか?
はい、そうです。映画祭以外では、川口の猫カフェに行ってきました。最高でした!その他にも友人に会ったり、楽しんでいます。
―今回の作品は既にあった原案をヤークトネスさんが脚本化したとのことですが、最初原案に触れた際の印象はいかがでしたか?
プロデューサーから最初、「愛せなくなった国際養子を祖国に返しに行く男の物語」という原案を聞いた時、不良品を工場に返すような扱いを子供にするなんて、なんてひどい父親なんだ、と思いましたが、考えてみれば、その過程でさまざまな出来事に出会い、父親が成長していくことを考えれば、非常に可能性を秘めたストーリーだと思いました。個人的に、似たようなケースもいくつか知っていました。脳に障害を持った子供を愛せない家族や、ただわが子の誕生に実感がなく、愛を注げない父。このお父さんは、それを恥ず事なく会社の同僚にを話すと、「そんなことを言ってはいけない!」とタブー視され、「どうしてなんだろう」と疑問を持っていました。よく母親が、産み落とした子供に愛情を持つまで時間がかかるとは言いますが、なぜ感情が持てないのか、あるいはそれをタブーとみなすのか、私個人として思うところもあった中、この映画の話をいただきました。
―国際養子縁組、世界の格差といった難しい問題を取り上げています。それぞれの子供の置かれる厳しい状況を感じる作品ですね。
いかに世の中が不公平か、ということ確かに描いています。ノルウェーであれば、子供には教育やモノの充実さ、という意味で大きな可能性が残されます。しかしコロンビアの子供は、スラムのようなゴミまみれのところで暮らし、シンナーを吸ったり、最悪身を売るといったことになりかねない。この映画はこういった色々な現実を伝えると同時に、感情に訴えかける、そういった役割を持っていると思います。
―現場、スタッフの雰囲気はいかがでしたか。
私自身は撮影には同行しなかったので伝聞した話なのですが、コロンビアのロケ地は治安が悪く、撮影をする為に常に武装した警備が必要なほどだったと聞いています。スケジュールがタイトだったり、環境の違いがあったりしたことから、体調管理が難しかったりもしたそうです。しかし監督は、地元の方たちや現地の雰囲気からコロンビアに惚れこんだということです。
―最後に読者のみなさまにひとことお願いします。
私のメッセージとしては、家族というのは複雑で、その形を保っている事というのは簡単ではない。たとえそれがうまくいかない時があったとしても、それを恥じないでほしい。自分がいい親じゃない、いい子じゃない、と思ってもそれは世界であなただけじゃない。他のみんなも感じている事です。家族という共同体の中で共存することは課題も多くあることなのです。長い目で幸せになる、ということは日々の犠牲のもと成り立っているものですから。
【取材・写真・文/坂東樹】