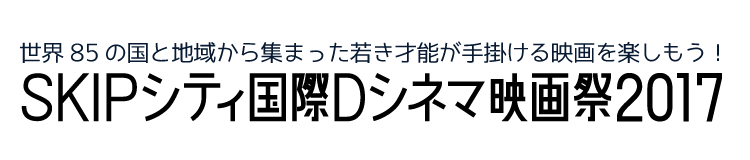息子を亡くしたエヤルとヴィッキー夫妻、彼らが迎えるユダヤ教の喪「シヴァ」最後の日から始まる感動作でメガホンを取ったアサフ・ポロンスキー監督に単独インタビューを行った。
ポロンスキー監督(以下、監督) 既に観光も済ませて満喫しています。日本にはずっと来たかったので良い機会になりました。
―SKIPシティ国際Dシネマ映画祭への応募の経緯は?
監督 釜山の映画祭で本作を目にしたプログラムディレクターが、是非この映画をSKIPシティに、と審査に持ち込んでくれたのです。
―コメディ映画というと、やはり観客のリアクションが気になります。映画全体の受け入れられ方として、ほかの国と違いはありましたか?
監督 もちろん行く場所が違えば反応も違います。あえて挙げるとすれば、特に印象に残るのはチェコです。大声で笑ったり、感動的なシーンではティッシュを取り出す音が聞こえたり、すべてのニュアンスを理解されているように感じました。その他には、釜山での上映ではダークな部分、ブラックジョーク的なニュアンスへの反応が大きかったように思います。
―映画のテーマとして「死と向き合う」ことが取り上げられています。初めて触れる宗教や文化の中での物語でも、とても自然に受け入れられました。どういった要素がこのような結果を生んでいると思われますか?
監督 クルーやキャストは、極限までイスラエル人の物語を目指して制作しました。ですから、文化的背景などに対する説明は必要ないわけです。そうして我々が普遍的であろうとしなければしないほど、物語の本質が問われるのでしょう。例えば私が日本映画を観たとして、見逃したりする点があるかもしれない、それでも楽しめるなら、それは優れた映画なのではないかと思います。
―この映画と、音楽というのが切っても切り離せない関係のように感じましたが、監督個人を含めその関係性はどんなものなのでしょうか?
監督 私自身、音楽のファンではあります。(インタビュー当日もキング・クリムゾンのTシャツを着ていらっしゃいました)劇中歌を探していて、タマール・アフェックというボーカリストの曲を見つけました。メールをして曲を使っていいか尋ね、OKを貰いました。元々彼らの曲を使うのは2か所と思っていましたが、編集段階で曲を流しながら作業をしていて、もっと使いたいと思うようになりました。スコアを書いてくれたのはいつも一緒にやっているラン・バグノでした。(タマールの曲と)邪魔にはならないけども、引き立て合えるような曲を作るのは簡単ではなかったですね。
―死生観という一つのテーマ、宗教や文化の違いが出やすいテーマのように感じられる反面、日本人としては受け入れやすく感じました何か理由は考え付きますか?
監督 特殊性、唯一性を突き詰めたからだと思います。クルーもキャストも普遍的ではなく、イスラエル人の観る映画のつもりで取り組んだからこそ、文化的説明などは必要なくなり、本質的なテーマがストレートに通じたのだと思います。例えば僕が日本映画を観たとして、わからないことや見落とすことがきっとある。それでも楽しめるのならそれは素晴らしい作品と言えますよね。
【取材・写真・文/坂東樹】