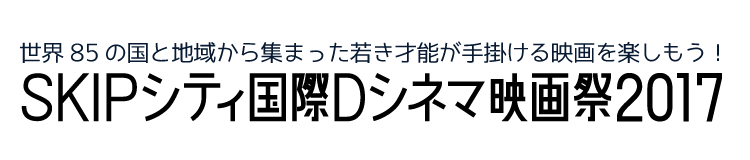長谷川 私は作品の担当で、大きな仕事としては、たくさんの応募をしてもらい、作品を集める作業をしています。今は海外の作品を担当していますが、もともと日本の作品もやっていたので、両面において応募者にアプローチをしたり、海外の映画祭に出向いて我々の映画祭の紹介をしたり、実際に映画を売っている会社とお話をしたりして、たくさんの応募を集めます。我々の映画祭では、一次審査員という予備審査をする方々がいらっしゃるのですが、その方々のご協力を得て、集めた作品を絞り込み、コンペティション作品を選びます。同時に、映画祭はコンペだけではないので、特集を企画したり、どういった作品を上映するかを決め、映画祭としてより魅力的なものを作る仕事です。
堀切 僕は映画祭の広報と宣伝を担当しています。パブリシティやプロモーション関係です。会期中は取材の対応がメインです。
―今年から始まる企画を含めて、本映画祭の見どころをお聞かせいただけますか?
長谷川 コンペティション部門は、長編・短編・アニメーションの3部門があります。アニメーションは今年で4回目とまだ回数は少ないのですが、3本柱となっています。それ以外に特集上映をやっています。長編アニメーションやバリアフリーの上映は毎年やっていますが、今年は特集企画として「飛翔する監督たち」があります。過去に我々の映画祭で映画が上映された監督たちが昨年から今年にかけて商業デビューを果たしたり、国内外の映画祭で話題の作品を作ったりしており、注目を浴びた監督たち6人をピックアップして、我々の映画祭で上映した映画を上映するという企画を組んでいます。VR特集もおそらく日本の映画祭で、国内外の作品を集めて上映するのは初めてではないかと思っています。我々はDシネマ映画祭として、35㎜での上映が中心だった時に、プリントではなくデジタルに特化して始めようということで、新しい技術に注目して始めた映画祭なのでVRもぜひということで、国内から2作品、海外から4作品のVR映画を集めて体験していただくという企画を行います。
―本映画祭から巣立った監督が活躍していくことについてはいかがお考えですか?
長谷川 もともとデジタルシネマに特化した映画祭で、プリントで撮影した映画よりも安価でできるということがあるので、より若手のクリエイターが作りやすいというのはあると考えていました。それが今はほとんどの映画がデジタルで撮られることにはなったんですけど、我々は若手の人たちが作りやすいというところで、デジタルに特化して始めたので、若手支援に注力をしてやってきました。活躍していってくださるのはありがたいですし、我々もできる限りのサポートのシステムを考えていきたいなと考えていきたいと思っています。
―今年のコンペティション作品の特徴は?
長谷川 全体として多かったのは、経済的な問題や難民・移民問題は海外の作品で多かった印象はあります。我々は観客を意識して作品を選んでいます。単純に“見せたいから”ではなくて、お客さんとインタラクティブに繋がっていきたいと思っているので、そういう意味ではお客さんに見ていただきたい、見せたいではなくお客さんを意識して見ていただきいという作品を選んだつもりです。映画としてはよく出来てるけど、日本の観客が見たときに難しいのではないか、理解しにくいのではないかという作品も多かったです。家族というのはどこでも共通のテーマなので、今年も家族の物語は多かった。ハンガリーの『市民』は、移民問題を真っ向から見つめた作品かつ人間ドラマが深いと思いましたので入っています。社会問題プラス家族の映画が中心になったのかなと思います。
―今回初めてノミネートされたアルメニア、スロヴァキア、ネパールの作品はそういったところの特徴に当てはまりますか?
長谷川 スロヴァキアとネパールの作品は社会問題を扱っています。スロヴァキアは厳しい貧困が根底にあって、犠牲者になっているのは子供たちだというドラマです。社会的な問題を根っこにしながら、最終的には一つの家族という集合体の意義を問うような作品です。我々にとってはグローバルにアピール出来るのではないかと思って選びました。ネパールの作品は内戦問題なので、少し特殊性はありますが、同じように子供たちが、誰が父親なのかという、ちょっと複雑な感情を抱いていくところは日本のお客さんでも理解しやすく、それを通してネパールの内線問題が長く続いて、今でも人々の生活に尾を引いているのかが分かる作品で、優れていると思いました。アルメニアの作品はエンターテインメントとして非常に優れていたというのが、我々の判断です。クライム・ドラマです。クライム・コメディかな?ラブストーリーも入っていて、スタイリッシュです。編集のうまさであるとか、プロの人とかは関係なく、一般のお客さんが見ていてものめり込んでいけるのが、映画としての魅力なのではないかと思っています。それと単純におもしろい、楽しめる作品です。
―今回で3回目となる映画祭が主体となって制作しているオープニング上映作品ですが、これまでの課題や今後の展望はありますか?
長谷川 制作支援は続けていきたいと思っています。今のスタイルが正しいかは置いておいて、そういったことは必要だと思っています。短編は安価なので撮れるけど、長編は撮れないという監督たちをサポートしたいというところからスタートした企画なので、制作支援は意義があることですし続けていきたいです。ただ、毎年オープニングでやっていて、制作期間の短さは感じるところではあるので、見直していくところが必要かと思っています。過去にDシネマプロジェクトというタイトルで、2011年から2013年に4作品の劇場公開をお手伝いしました。それは意義があったなと思っています。配給支援の第三弾が中野量太監督の『チチを撮りに』という作品で、今回「飛翔する監督たち」にも入っています。2013年の『神奈川芸術大学映像学科研究室』の坂下雄一郎監督もこのプロジェクトで、劇場公開をお手伝いさせていただきました。坂下監督は今年『東京ウインドオーケストラ』で、松竹ブロードキャスティングのオリジナル映画製作プロジェクト第三弾に抜擢されて商業デビューしました。劇場で上映されることで、監督の名前とかが出ていくと思うので、オープニング作品の制作支援だけではなくて、そういった配給支援もぜひやりたいです。作るだけではなく、よりお手伝いができるような形にしたいと考えています。
―オープニング作品はどれくらいで撮影していますか?
堀切 撮影自体は10日間くらいなのでだいぶタイトですね。
長谷川 来年は15周年なのでより大型の形で出来ればと思ってはいます。お約束はできないのですが(笑)
―『東京ウインドオーケストラ』の宣伝活動をしてますよね。
堀切 もともとDシネマプロジェクトで配給支援をしたので、坂下雄一郎監督を知っていたというのと、Dシネマプロジェクトが新宿武蔵野館で公開をしていたんです。配給支援をするといっても劇場の協力がないと難しい中で、協力してくださっていた。『東京ウインドオーケストラ』も新宿武蔵野館での公開を予定していた。その中で推薦していただいたというお話なので、映画祭の事業とは別にやっていました。結果的にきっかけにはなってますね。
―今回審査委員長を黒沢清監督が務めていらっしゃいますね。
長谷川 映画祭の審査員をあまり受けたことがないということです。(本映画祭の)土川勉ディレクターが、黒沢監督の作品を過去にプロデュースしているという縁で、引き受けていただくことが出来ました。我々が若手支援を標ぼうしているということで受けてくださったと思います。
―ドイツの日本映画祭「ニッポン・コネクション」との提携はどのようにして生まれたのですが?
長谷川 昨年はオランダで開催された「カメラ・ジャパン」との提携があってプログラミングディレクターを招待して作品を観てもらい、我々の作品をあちらの映画祭で上映していただくという提携をしていました。我々としてはいろいろな海外の映画祭と繋がっていくことで、我々が選んだ作品が上映され、彼らの次回作が広がっていくことを期待しています。その中で、今年は日本映画祭の中でも世界最大であるニッポン・コネクションと提携するという企画が生まれた。
―今年の5月に開催された「ニッポン・コネクション」では、本映画祭に関連する作品も多く選出されましたね。
長谷川 やり取りは今年だけではなく長い間やってきて、我々で上映した映画を観ていただいていました。もちろん彼らが選ぶという立場なので、その中から選んでいただく形になります。若い監督を知りたいという気持ちはあるので、それは映画祭としての繋がりという意味ではあると思います。中野監督や坂下監督の作品も上映されたこともあります。
―来年(2018年)は15周年ということでなにか新しくしていくところはありますか?
長谷川 プログラミングの立場としては、幅広いお客さんに観てもらえるための企画を考えています。映画祭全体としてはこれから考えていくところになるかと思います。
堀切 昨年から土川ディレクターが就任しが、今年で14回を迎え、来年は節目になります。始まった当時はデジタルシネマがまだまだ浸透していない状態でしたが、今では映画=デジタルシネマという時代になった。Dシネマ映画祭というものがどう位置づけられるのか、いずれ課題として挙がってくる部分ではないかなと思います。若い監督を育てるというところをやってきた中でうまくいったこともあるし、思っていた結果が出せなかったこともある。区切りになるので改めて精査して、映画祭としてできることを見直すということは我々のスタンスとしては必要だと思います。
―上映時間の都合でいけないという意見もあるようですが、上映回数を増やす予定はありますか?
長谷川 映画祭をより大きくしたいという気持ちはあるので、見ていただく機会を増やしたいのですが、そのためには組織自体を大きくしていかなければいけない。夜終わるのが早いというのはありますが、今の体制ではこれが精いっぱいです。選んでいる作品はお客さんのことを考えて、と言っている割にはというところがあるので、どういった形が観ていただきやすいのかは課題としてあると思っています。
堀切 会場はサテライト上映もありますが、SKIPシティではいま会場が2つしかないので、スケジュールの枠がいっぱいというのが現実です。具体的にどうというのは決められていないですが、アンケートでも「レイトショーをやってほしい」「日数を増やしてほしい」という要望をいただいていることは事実なので、どこまでお応えできるかはわかりませんが、応えていけるようにしたいと思っています。
―今回はHDスタジオも使っていますね。
堀切 普段は撮影で使っているスタジオに、映画祭の期間中だけVRの機材を持ち込んで上映します。イベントでもお客さんに入っていただけるようにしたいと思っています。
―ほかの映画祭と比べて魅力というところは?
長谷川 我々がアピールしたいのは、映画の内容としてもお客さんが楽しんでいただける映画というのを念頭に置いて選んでいます。難しい映画がいけないというわけではなく、排除しているわけでもありませんが、映画祭でやっている映画は難しいんじゃないかということや、敷居が高いんじゃないかというイメージを持たれてしまわないような映画を念頭に置いています。たくさんのお客さんに見ていただきたいです。今回上映される海外作品は全て日本初上映で、これまでに日本で公開される機会がなかった作品です。劇場で公開されることや特集上映がされる機会がない、それでもたくさんのお客さんに観ていただける作品は世界中にたくさんあると思います。そういった作品をたくさん観ていただいて、楽しい映画をやっているんだというイメージで、次の映画祭にも来ていただきたいですし、監督の今後にも注目していただきたいです。
堀切 日本で公開されていない海外の映画を上映するのは国際映画祭の役割のひとつでもあります。ジャンルや国を限定していない国際映画祭は、日本では比較的少ない印象があります。それが他と比べていいかどうかは別にして、珍しいのかなという感じはあります。
長谷川 ノミネートが4作品目までというのはありますね。
堀切 若手監督に絞っているのは特色ですね。都心でやっている映画祭ではないので、地元の方がふらっと見に来たりもする。身近な映画祭というか、今は映画自体を見に行かない方もたくさんいらっしゃる中で、映画祭は小難しかったり、映画ファンでしか分からないという印象を持っている方も多いと思います。そんなことない、もっと気楽に来て楽しめるところですよということをアピールしていきたいと思っています。
長谷川 あと長編・短編・アニメーションという3つのコンペティションを持っている映画祭もあまりないと思います。
―最後にこれから本映画祭に期待している方々へメッセージをお願いします。
長谷川 「飛翔する監督たち」もそうですが、我々の映画祭でやった映画や監督が広がっていってほしいという気持ちは常に持っていて、今年も昨年上映された『アウト・オブ・マイ・ハンド』が『リベリアの白い血』というタイトルで劇場公開されます。昨年のグランプリ作品と監督賞の作品が「カリコレ」で上映されます。こういった形で我々の映画祭を経由して、広がってほしいという気持ちを持っています。今後そこにも期待していただきたいですし、たくさんのお客さんに来ていただくことでそういったことが実現するということもあるので、たくさんの方に来ていただきたいです。
堀切 劇場で公開される映画もそうですが、映画祭はより監督たち、応募する方や、見に来てくれる方がいないと成立しないものだと思います。監督たちに必要とされ、お客さんにも期待される映画祭になっていけるようになればいいなと思っています。15周年に向けてよりパワーアップしていきたいと思っています。立地的に遠いイメージを持たれるかもしれませんが、来てみるとそれほどでもないかと(笑)チラシやサイトを見ていただいて、少しでも気になる作品があれば、ぜひ一度来てみていただければと思いますし、気楽に来れる映画祭でありたいと思っています。